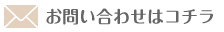「痛みと共に居て、私が感じたこと」
掲載日:2025.10.07
今回は、クライアントのEさんの体験談です。
セッションを開始したころのEさんは、なかなか感情と共にいることが難しい人でした。
「感じてみて」と言っても、「思考」がかえってくる人でした。
なかなか効果が感じられないEさんに、私は、
「しびれを切らしてセッションをやめてしまうかもしれない」と思っていました。
ところが、ここ数か月のEさんは、目に見えて「感じる」ことが上手になり、
毎回私が「すごい!」と思うような変化を見せてくれています。
Eさん自身が自分をあきらめずにセッションを継続してくれたおかげだと思います。
今回の体験談は、まさにその
「継続セッションのプロセスでどのような体験をしたか」が描かれています。
ある日、私はセッションの最後にEさんに「宿題」を出しました。
そして、翌週Eさんは、それについて報告してくれました。
それを聞いて私は、「想定した以上の素晴らしい体験!」と思いました。
このプロセスを言葉にするのは難しいと思いましたが、
Eさんに「もし書けたら書いてみてほしい」と、お願いしました。
そしてEさんから送られてきたのが以下の文章です。
この文章も、私が想定していた以上にご自分の葛藤や心の変遷が丁寧に描かれていて、
「ここまで描写してくれたのか」と、ちょっと感動してしまいました。
これを読んで「わかる」「私も同じ」と思う方も多いのではないでしょうか。
あるいは「発達性トラウマ」の「反応」や「衝動」を理解する一助になるかもしれません。
Eさんの文章の後に、私からの蛇足を少し載せました。
・・・・・・・・・・・・・・・
私は、「失敗」というものにひどく落ち込みやすい。
年齢を重ねていくごとにその心の反応は、ますますひどくなっていったように思う。
特に「失敗」の種類の中でも、他者が関わる内容だと、その反応はさらに大きくなる傾向にあった。
そんな私はまず、「失敗」に気づくと居ても立ってもいられない衝動に駆られる。
それは、一瞬で体から溢れてしまいそうな勢いで胸の奥から溢れてくる。
その勢いに呑まれてしまうと、
「だってこんなの〇〇だから防ぎようがないじゃない!」
とか、
「そもそも〇〇さんだってこうしてくれれば…。」
といった言い訳や責任転嫁の言葉で、私の頭と心は埋め尽くされてしまう。
しかし仕事仲間や友人に対して、実際にそんな言葉をぶつければ、信頼を失うことも当然理解している。
そこで次に私がとる行動は、「過剰なほど謝る」というものだった。
相手が「気にしていない」、もしくは「許してくれた」という確信を得るまでへりくだり、自分で自分を責めている姿勢を見せるのだ。
そして社交辞令でも相手が「自分にも責任はあった」といった内容の発言をしてくれることを期待した。
実際に多くの優しい大人は私の期待通りの反応をしてくれた。
それは、これ以上自分の心が傷つかないための防波堤のようなものだった。
だから私は、この姑息とも言える行動をとることで、この衝動的な感情とどうにか折り合いつけることができるのだった。
しかし、不器用なりに保ってきたこのバランスが大きく崩れたのは、子どもが生まれて母親になってからだ。
私が管理し、考えなくてはならないことが、自分に関することだけでなく、子どもに関わるものまで広がってしまったことが大きかった。
特に「母親」という役割に関する「失敗」の辛さは、さらに私の心をえぐった。
その失敗には必ず、「子ども」と「子どもの周囲にいる大人」という他者が関わってくるからだろう。
さらに私は、無意識ながら「よい母親」に見られたいという思いが強かった。
せめて人並みに「ちゃんとしている母親」と思われたかった。
抱える責任が増えた上に、当然母親としての経験値が少ないため、あらゆることが手探りで、戸惑いや分からないことだらけの中で、やらざるを得なかった。
必然的に「失敗」も増えた。
それは子どもの持ち物の管理であったり、予定の管理であったり。
そういったことを保育士などに優しく指摘されただけでも、私はそれを「母親としてありえない失敗をしてしまった」という気持ちになる。
そしてまたあの辛い感情が湧き上がる。
それに堪えられなくなった私は、いつからかその感情を子どもにぶつけるようになっていた。
「そもそもあなたがちゃんと言ってくれないから!」
「あなたのことでしょ!なんでそんなこともできないの!」
「ママはこんなにがんばってるのに!」
今までは心の中や独り言で留めていた、失敗を正当化し責任転嫁する言葉を、幼い子どもたちにそのまま言い放ってしまうようになった。
さらに子どもがした他の小さな失敗を、必要以上に責め立てることで発散するようになってしまっていた。
そして、その後は決まってぞっとするのだ。
その「言い方」や「責め方」が、自分が苦手だった実母の叱責にとても似ていることに。
あれほど、そうなりたくないと思っていたのに。
そしてそのようなヒステリーを起こしては、それを後悔してまた苦しむという悪循環から、私は抜けられなくなっていった。
今、その時の自分を振り返ってみると、自分を無条件で必要とし続けてくれる存在、つまり私を絶対見捨てないであろう「子ども」という存在に甘えていたのだと思う。
ちょうどいい捌け口を見つけてしまったのだ。無意識のうちに。
でもそもそもどうしてそのような「衝動」に駆られるのか。
私は辛さを感じつつも、深く考えることも考えようとすることもしなかった。
ただ、「こんなつらい思いをしたくないから、もっとちゃんとしなくては。」と同じ結論に至るだけだった。
そしてまた失敗しては苦しむということを繰り返していた。
紀代子さんとのセッションを始めるまでは。
セッションでその日話すテーマを決める中で、何回かこの「失敗に堪えられない自分」について話す機会があった。
その中で私は、「失敗」そのものよりも「失敗」によって他人に失望されることを恐れていること、しかもその失敗を実際に一番強く責めているのは内面の自分自身であることが、徐々に分かってきた。
しかしこの言いようのない辛さに「堪えられない」原因は、失敗した事柄にこだわってしまうからだと私は思っていた。
しかし、先日の紀代子さんとの会話の中で、失敗の原因を他に探そうとしたり、無理矢理「たいしたことない」と自分に言い聞かせたりする「辛さに留まれない自分」がいることに気づかせてもらった。
そのセッションの終わりに紀代子さんから
「そこに留まって、その痛みと一緒にいることを意識してみて。」
という『課題』を出してもらった。
正直できる自信はなかった。
なぜならその「反応」は一瞬で巻き起こる上に、そうしないと堪えられないほどの激しい衝動だったからだ。
しかしそのセッションから少し経ったある日、いつものように私はまた、小さな「失敗」をした。
失敗した内容が私にとって比較的「小さな」ものだったのも幸運だったのかもしれない。
でも私は、いつものように煮えたぎる濁流のような反応を腹の奥に感じた。
けれどその次に、紀代子さんとの『課題』をすっと思い出すことができたのだ。
私は初めて濁流の中で立ち止まろうと意識できた。
そして自分に言い聞かせるように
「ここに居る…この痛みと一緒に居る…」
と、心の中で何度か呟いてみた。
その呟きを繰り返しているうちに、気づくと私は今まで感じたことのない不思議な感覚に包まれていた。
言い訳や責任転嫁の言葉が渦巻いている時は、その失敗が原因で「得体のしれないとんでもないこと」になってしまいそうな不安や恐怖を感じていた。
しかし今回留まって痛みとともに「居る」ことで、失敗による「本当の痛さ」を感じることができたのだ。
すると、私が怯えているほどの「得体のしれないとんでもないこと」など「ない」ということが、少なくとも「そこまでたいしたことではなかった」ということが理解でき、心の奥で失敗を責め立てる自分自身を納得させることできたのだ。
そして私の心の反応はゆっくり静かになり、その失敗の事柄に応じた範疇に治まることができたのだ。
本当に不思議な感覚だった。
あれほど止めたくても止められなかったことが魔法のようにあっさりとできてしまい、どこかあっけにとられた気持ちにさえなった。
このささやかな成功体験は、今までずっと私を閉じ込めてきた暗くて狭い部屋に、一筋の光が差し込むような、小さいけれども確かな安心感を与えてくれた気がする。
とはいえ今の私も、この「痛みと居る」ということが毎回できているわけではない。
先に反応が出てしまい、さんざん子どもにヒステリーを起こした後で気づくこともある。
けれど良いのか悪いのか…そうした後に起こるひどい自己嫌悪の悪循環も、不思議と前より穏やかになったように思う。
それはこの体験を通して、「得体のしれないもの」の輪郭が、少し見えるようになったからかもしれない。
だからやりすぎてしまった場合は、後で気持ちが収まってから子どもたちに心から謝ることができるようになったように思う。
まだまだ私には、「人並みにちゃんとしているか」ということばかりに囚われていたせいで、見ないふりをしてきた「得体のしれないもの」がたくさん心に積み残されていると思う。
それをこれからもセッションを続けていく中で、少しずつ立ち止まって知っていきたい。
そうすることで一人の大人としても、子どもをもつ親としても、「ゆとり」をもって生きていけるようになれたらいいなと思っている。
・・・・・・・・・・・・・・
多くのクライアントさんたちは、子ども時代に親から否定や拒絶を受けてきています。
そこには悲しみや怒りという感情があったはずです。
しかし、親の前でその感情を出すことは更なる叱責や拒絶にあうため、
子どもにとっては「危険」となります。
そこで子どもは徐々にあきらめ、自分の感情を感じないようになります。
しかし、感じないように封印された感情は深い部分に残っています。
この封印された悲しみや怒りの感情は、大人になってから
ちょっとした刺激でよみがえります。
失敗(と自分で思ったこと)をしたことで
瞬間的に過去に親から叱責されたり拒絶されたときに感じた
悲しみや怒りがよみがえりそうになります。
この時、「それを感じてはいけない」と無意識が瞬間的にそれを避けようとします。
これは「悲しみや怒りを感じると危険だ」という過去の経験から来る恐れです。
しかし、大人になった今は、自分の感情を感じても危険なことはまず起きないでしょう。
Eさんは瞬間移動であっという間に別のところに気持ちが行ってしまうので、
「失敗を感じた時に、ちょっと頑張ってそこにいてみて」と課題を出しました。
そしてEさんは「小さな失敗」の時に私の言葉を思い出して、
煮えたぎるような濁流の中で立ち止まろうと意識できました。
よくできましたね、Eさん! はなまるです❣
そして今回は、この「小さな失敗」が大事でした。
小さくないと、恐怖のほうが大きくて耐えきれなくなる可能性があったので、
「小さな」という条件を付けました。
この課題を、Eさんはとても上手に実行してくれました。
「一瞬で巻き起こる『反応』、そうしないと堪えられないほどの『激しい衝動』」。
そこにEさんは立ち止まろうと意識し、それができました。
セッションの中で「そこにいる」ことを繰り返し試みてきた成果です。
そこにとどまってみると、Eさんの言うところの「得体のしれないとんでもないこと」は
「無い」か「そこまでたいしたことではない」ということに気づきました。
「その感情を感じると恐ろしいことが起こる」という恐怖は、
過去の経験から来る「未来予測」です。
今、Eさんは、その過去の痛みから来る「未来予測」を少しずつ上書き修正しているところです。
正しく修正されていくと、過去から持ち続けてきた恐怖から解放されて、
起きたことを等身大に受け止められるようになります。
緊張感から解放された人生が送れるようになります。