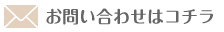「複雑性トラウマ」「発達性トラウマ」への理解
掲載日:2025.04.08
私のクライアントさんのほとんどは「発達性トラウマ」を抱えてきた人と言えます。
私は「精神的虐待を受けて育った人」と思っていますが、
ほとんどの人は「虐待を受けたわけではない」と言います。
誰だって自分が虐待を受けたなんて簡単には受け入れられないと思います。
でも話を聞いていくと、やはり「精神的虐待」だと私は思います。
常に親の意向や機嫌を最優先にして子ども時代を過ごさざるを得なかった。
それは子どもとして「安心・安全」を感じて育てなかったということです。
前回書いたように、子どもは100%親に依存しているので、
親に見捨てられることは恐怖でしかありません。
それは意識的に「そう思う」というよりは、
無意識で「そう感じる」のです。
そうして子どもの無意識は、「親に見捨てられないように」親の意向を最優先し、
自分自身の「気持ち」や「感覚」や「思い」は封印します。
簡単な例を挙げると、
小学校低学年の子どもが親にTシャツを買ってもらうためにお店に行った。
母親は「好きなものを買いなさい」と言った。
その子は緑色が好きで、緑色のTシャツを手に取った。
その瞬間、母親の顔つきが険しくなるのを察知する。
その子はすぐに緑のTシャツを手放し、母親が気に入るであろうピンクのTシャツを手に取る。
母親の顔は満足げになり、その子はホッとする。
そんな「小さなこと」と思われることが日常で繰り返されます。
そこで子どもが無意識に学ぶことは
「自分の欲求や感情を持ってはいけない」ということです。
自分の欲求や感情を持つことを否定され続けると、
「自分の欲求や感情」と繋がっていることは苦痛でしかないので、
繋がっていることに耐えられなくなりそれらと断絶します。
親の不機嫌は、子どもにとっては想像以上に恐怖です。
自分の本当の気持ちを遮断して感じなくすることが、
親から見捨てられる恐怖から解放される唯一の道だと確信していきます。
これは親に依存しなければ生きられない子どもにとっての「適応戦略」と言えます。
それらは子ども時代には自分を守るために役立ちましたが、
大人になってからの日常や人生には支障をきたします。
そうやって大人になった人は、他人や自分との関係がうまくいきません。
基本となる「自分」がよくわからないからです。
「何が好きか」「どんな気持ちか」「どうなりたいか」などを問われても
最初のうちはみなさんうまく答えられません。
上手にできるのは「他人の意向をくみ取ること」です。
常に「他者は自分に何を求めているか」に気を張っています。
ですから他人といてクタクタになってしまいます。
リラックスしていい場(飲み会やお茶会など)でも、人に気を使います。
帰ってきてからも
「あんなことを言って気を悪くしたのではないか」
「もっと気の利いたことを言えばよかった」などなど
後悔ばかりして落ち込みます。
「自分がどうしたいか」ではなく、「相手が望んでいる」であろうことを言ったりしたりする。
こんなことが続けば、疲れ果てて生きるのがしんどくなるのは当然です。
自分の人生を自分以外の人のために捧げていると言えます。
自分の気持ちや時間や労力や、時には性さえも提供します。
自分の中に自分はいなくて、他人がたくさんいるような感じです。
「あの人の言葉」「あの人の価値観」そんなものばかりが占めています。
私のセッションは、そんな「見失った自分」「奪われた自分」を取り戻す時間とも言えます。
「発達性トラウマ」を抱えた人たちは、
大人になっても様々な症状で苦しみます。
無価値観(自分は生きている価値がない)、自責の念(自分が悪い)、
希死念慮(死んでしまいたい)、過剰適応、他者への異常な気遣い、
自分の感情がわからない、感情の起伏の激しさや感情のコントロールの難しさ、
などがあります。
自傷や、他者から被害を受けることに脆弱であったりもします。
現在日本の精神科や心療内科で行われている心的外傷後ストレス障害(PTSD)という診断は、
大きな事故や災害・犯罪など主に「単回性ショックトラウマ」による症状に対してのものです。
それにさえ十分に対応できている病院やクリニックはどれだけあるでしょう。
トラウマの原因として大きな劇的な出来事に焦点が当たり、
より身近な日常的にあるトラウマに苦しむ人たちには適切な知識やケアが届いていません。
「複雑性トラウマ(発達性トラウマを含む)」に苦しむ人たちが抱える生きづらさは深刻です。
対人での支配的な関係性に長期にわたり置かれることから、
単回性の惨事で生じるPTSDの症状(フラッシュバックや回避など)に加えて、
「自己の無価値観や無力感」「対人関係の困難さ」といった生きづらさに長く苦しみます。
「複雑性トラウマ(発達性トラウマ)」を抱えている人は、
現在の「単回性トラウマ」に対するPTSD治療によって
かえって重篤な結果になる可能性があることも指摘されています。
「発達性トラウマ」や「複雑性トラウマ」を抱えた人たちの苦しみや生きづらさを
理解できる専門職は、まだまだ少数であることをいつも痛感します。
私が自主的に行っている全国ネットでのオンライン勉強会では
「発達性トラウマ」の理解やケアを身につけたいという意欲的な人たちが参加していますが、
病院勤務の臨床心理士・公認心理士たちは、
自分たち心理士も含めて精神科・心療内科の医師が
「発達性トラウマ」や「複雑性トラウマ」に関しての知識も認識も無い人が多いと嘆いています。
ごく少数ではありますが、(児童)精神科医の中には知識や理解を持つ人もいますが、
日本全国で見ると、まだまだ稀だと感じます。
知識や理解がなければ、対処療法的に薬を出すしかなくなります。
薬では根本的な解決にはなりません。
せいぜい出来て「言葉による」カウンセリングです。
カウンセリングももちろん一定程度は有効です。
共感や理解を示されるだけで癒しにつながることは多いです。
でも「カウンセリング」では、「複雑性トラウマ(発達性トラウマ)」を抱える人たちの苦しみを癒し、
再生に向けてサポートするには不十分だと私は感じています。
精神科医療に携わる人たちのアップデートが進み、
複雑性・発達性トラウマを抱える人たちの苦しみを理解し、対応できるプロが増えることを願います。