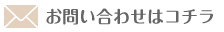「虐待」という言葉
掲載日:2025.07.29
Mさんの【お祝い】というコラムの前書きに私が寄せた文章について、
Mさんから疑問が寄せられました。
Mさんの言葉を載せてみますね。
・・・・・・・・・・・・
「自分は虐待を受けた」とは思っていなくて、
むしろ私の人生では普通のことなので「この程度で過酷とか恐縮です」感があります。
自傷行為も「たいしたことないんですけど」って感じです。
それなのに、紀代子さんの「どれほど過酷で困難なことであったか」という言葉に
意味も分からず涙が溢れました。
紀代子さんが前に書いた「発達性トラウマ」についても、
私はフルコンポ(すべての条件を満たしている)しているけど、
「いやいや、大げさですよ」と、「たいしたことない感」になります。
・・・・・・・・・・
このように言うMさんは、「体感と脳が解離している感じがある」ので、
それをセッションのテーマにしたいと言ってくれました。
[そこに気づけるようになって、それを言葉にできるようになった]。
Mさんの気づきのセンサーが磨かれ、
その疑問に踏みとどまれるようになったことをとても嬉しく感じました。
45分間をフルに使って、そのテーマについてMさんと深めました。
そもそも私は「虐待」という言葉をあまり使いません。
クライアントさんが受けた理不尽さに気づいてもらうために
ごくまれに「それって虐待だと思いますよ」と言うことはありますが。
あまり使わない理由の一つには、「虐待」という言葉の持つイメージが
社会的にけっこう固定されているような気がするからです。
「そのイメージに自分は当てはまらない」と感じられると、
そこから先に進めなくなってしまうということが起こるので、
私はあまりその言葉を使いません。
「私は虐待は受けていません」と言いながら、
Mさんのように自傷行為を繰り返したり、依存症に陥ったり、
希死念慮にさいなまれたりしている人、
あるいは「自分は生きている価値がない」と感じている人には、
「あなたは子ども時代、安心して安全に過ごせましたか?」と尋ねます。
そう尋ねられると、ほとんどのクライアントさんは「緊張」「不安」「怖れ」「心配」「混乱」
そして「自分の存在を恥じる感覚」などの中にいたことを思い出します。
大事なことは、「虐待」という言葉ではなく、
「どのような心理的状況で育ったか」ということです。
かなり回復したMさんであっても、
「私が悪い子だったから」という思いはまだ残っていて、
「あれは躾だった」という言葉さえ出てくることがあります。
これは多くのクライアントさんに共通することですが、
自分が受けた理不尽な行為を「自分が悪かったから」と思い
「悪い子に罰を与えた親は悪くない」と心のどこかで思い続けていることは珍しくありません。
これは、親から「お前が悪い子だから」と親自身の行為の正当化が行われたことも大きな理由です。
そして自分の抱えている辛い症状も「たいしたことはない」と
軽くとらえようとすることも特徴です。
想像してみてください。
親の感情の起伏が激しくて、
どこに感情爆発の地雷が埋まっているかわからない状態で
その地雷を踏まないように緊張しながら暮らす子どもの気持ちを。
思い通りの言葉を言ったり行動をしないと
不機嫌になったりぶち切れる親の機嫌を損ねないように
常に先回りして親が満足する言動をしなければならない子どもの気持ちを。
子どもの望みではなく、親自身の欲求を優先し、
子どもは自分のために使う「モノ」扱いの親の元で育つ子どもの気持ちを。
常に不機嫌なオーラを発している親のそばで
身が縮むように暮らす子どもの気持ちを。
自分の楽しみや興味にしか関心がなく、
最低限の衣食住は与えても、子どもの心への配慮はなく、
まるで存在は無いものとして扱われながら生きている子どもの気持ちを。
他のきょうだいは可愛がられ親と笑顔で過ごしている傍らで、
自分だけは冷たい視線を向けられ、きつい言葉をぶつけられ、
病気になっても思いやりも示されず
一人で耐えるしかなかった子どもの気持ちを。
そのような子ども時代を過ごしてきた人は、実はたくさんいます。
たとえ身体的な暴力は無くても、
そのような環境に子どもを置き続けることは、
どれほど子どもの心を傷つけ蝕んでいくことでしょう。
頭では「たいしたことはない」「私が悪かったから」などと思ったとしても、
たった1行の文章を目にしただけで、たった一つの言葉を聞いただけで、涙があふれ出す。
これが答えです。
頭は洗脳されるし嘘をつくけれど、
身体は正直で本当のことを知っています。
だから私はセッションで、よく「身体の感覚に気づいてみてください」と言います。
言葉では「大丈夫」と言っていても、身体はこわばっていたり痛みを感じたり、
吐き気をもよおしたりしています。
身体は「大事なこと」「その人にとっての真実」を伝えてくれているのです。
政府の行政機関の一つに「こども家庭庁」があります。
「こども家庭庁」のホームページには、以下のように書かれています。
[こども家庭庁は、こどもがまんなかの社会を実現するためにこどもの視点に立って意見を聴き、
こどもにとっていちばんの利益を考え、こどもと家庭の、福祉や健康の向上を支援し、
こどもの権利を守るためのこども政策に強力なリーダーシップをもって取り組みます。]
これが無意味とは言いませんが、私には全く響いてきません。
言葉遊びやきれいごと、表面的なやってる感しか伝わってきません。
予算をつけてやるなら、子どもたちにとって真に有効な施策を取ってほしいです。
「家庭の中で人知れず傷ついている子ども」を救い出せる社会になることを願っています。